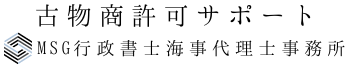個人の古物商の多くは、自宅を営業所としている場合が多いでしょう。
この自宅兼営業所を引っ越す際には、事前届出と事後届出の2つの手続きが必要です。この記事では、事前届出に必要な書類の書き方について詳しく解説します。
事前届出の用紙はどこで入手する?
事前届出は、具体的には変更届出書 別記様式第5号により届け出を行います。この用紙は各都道府県警察のホームページからダウンロードが可能です。
東京都の様式については、警視庁のホームページ又は以下のリンクからもダウンロードができます。
変更届出書(別記様式第5号)の書き方
記載例は、個人で許可を受けた古物商が、自宅を営業所にしているケースです。この自宅兼営業所を移転する場合には、以下のように記載していきます。

①宛名
宛名は、変更後の「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」です。
記載のケースでは、東京都から神奈川県に移転するため、宛名は移転先の所在地を管轄する「神奈川県公安委員会」と記入しています。もし、福岡県から佐賀県に主たる営業所を移転する場合には、宛名は「佐賀県公安委員会」です。
もし、同一の東京都内での移転であれば、宛名は「東京都公安委員会」となります。
変更届出書の提出先は、主たる営業所(引っ越し前)の所在地の所轄警察署となります。もし主たる営業所のある都道府県以外の都道府県にも営業所がある場合には、その営業所の所在地を管轄する警察署にも提出することもできます。
②提出年月日
この日付は、作成年月日ではなく、提出年月日です。
実際に提出した日付を記入する必要がありますので、警察署の窓口へ行くまで空欄としてください。
③届出者の氏名又は名称及び住所
届出をする者の住所と氏名を記入します。住所は古物商許可証に記載の通りに記入しましょう。
④許可の種類
許可の種類には、「1.古物商」の数字部分を丸で囲みます。
記載要領では「数字を付した欄は、該当する数字を丸で囲むこと。」とのルールがあります。したがって、「1.古物商」のような数字のある選択欄はすべて数字部分を丸で囲むようにしましょう。以下同様です。
⑤許可証番号
ここには、許可証に記載されている12桁の許可証番号をそのまま記入します。
⑥許可年月日
許可証に記載されている許可年月日をそのまま記入します。
⑦氏名又は名称
ここでも、許可証に記載の通り記入します。
氏名のフリガナは、姓と名の間は一マスを空けます。
また、濁点(゛)や半濁点(゜)は1マスを使用します。そのため、例えば「ブ」を記入する際には、「フ」と「゛」の2マスで記載します。
⑧住所
移転前の住所を記入します。許可証に記載されている通りに記入していきます。
⑨変更区分
記載例では営業所の引っ越しが届出の目的なので、「2.変更」の数字部分を丸で囲みます。
⑩変更・廃止する営業所又は古物市場の名称
変更する営業所の屋号を記入します。屋号を設定していない場合には、申請者の氏名を記入します。
ここでも、氏名のフリガナは、姓と名の間は一マスを空けます。濁点(゛)や半濁点(゜)は1マスを使用します。
⑪変更予定年月日
営業所の移転予定日を記入します。自宅兼営業所の移転の場合、新住所への転入日です。
変更予定年月日の3日前までにこの書面を提出する必要があります。3日前とは、中3日を指しますので、実際には4営業日前が提出期限となりますのでご注意ください。
⑫主たる営業所・古物市場
・「形態] ……「1.営業所あり」の数字部分を丸で囲みます。
・「名称」……営業所の移転の場合にはここは空欄にします。ここでは変更となる箇所のみに、変更後の内容を記載しますので、名称を変更しない場合には空欄にします。
・「所在地」……移転先の所在地を記入します。電話番号についても、変更が無ければ空欄で構いません。
主たる営業所に関する変更は⑫に記入しますが、その他の営業所に関する変更であればこの内容を⑬に記入してください。
⑬その他の営業所・古物市場
記載例のケースでは主たる営業所に関する変更であるため、⑬は空欄とします。
このように主たる営業所の所在地の変更は⑫に変更事項を記入しますが、その他の営業所(営業所が複数存在する場合で、主たる営業所以外の営業所)の所在地が変更になる場合は変更事項を⑬に記入していきます。この場合には逆に⑫を空欄とします。