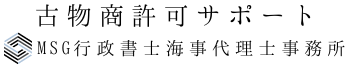最近では、副業や個人として古物商を始める方が増えており、それに伴って「自宅を営業所として古物商許可を取得したい」という相談が非常に増えています。
特にインターネットを使用した中古品売買が主流になりつつある中で、わざわざ事務所を借りずに、自宅から始めたいと考えるのは自然な流れです。
このページでは、これから古物商許可をご自宅で取得しようと考えている方を対象に、「自宅を営業所にする際に押さえておくべきポイント」や「よくある注意点」について、行政書士の実務視点から解説します。
自宅での申請の可否が心配な方や、具体的に何を準備すればいいのか迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください。
自宅で古物商許可を取ることは可能?
結論:自宅でも古物商許可は取得可能です
自宅を営業所として古物商許可を取得することは可能です。
実際、多くの方が自宅を利用して申請を行い、許可を取得しています。近年はインターネットでの中古品売買が盛んであることから、副業や小規模な個人事業を始めたい方にとっては、コストを抑えながら古物営業を開始できる選択肢としてポピュラーな方法となっています。
賃貸借契約書や使用承諾書は必要?
古物商許可の手続きにおいては賃貸借契約書や使用承諾書は原則不要です。
ただし、ご自宅が賃貸物件の場合、賃貸借契約書に記載の目的欄が「事業用」であれば何ら問題ありませんが、「居住用」等の記載がある場合、規約上は大家さんからの承諾が必要になるケースがあります。
古物商許可の申請上は、原則使用承諾書や賃貸借契約書の写しを求められませんので、「居住用」の賃貸であっても許可を取得することは可能です。
東京都や神奈川県等の大都市圏においては、使用承諾書や賃貸借契約書の提出まで求められませんので、使用承諾を得ていない場合には大家さん等との関係は自己責任で古物商許可を受ける形となります。基本的には使用承諾を得るよう心がけましょう。
これは個人申請でも法人申請でも特に変わりません。
法人で古物商許可を申請される方で、ご自宅を営業所にする場合でも、基本的には賃貸借契約書や使用承諾書の提出は求められることは原則ありません
警察署による運用差が大きい
東京都や神奈川県など大都市圏の警察署では比較的柔軟な運用で、営業所についてもある程度自己責任の側面がありますが、滋賀県や長野県、宮城県など一部の地域では、使用承諾書の提出によって書面により使用承諾の有無を確認されます。
原則は最初に警察署に電話確認
このように管轄によって運用は変わるため、管轄警察署に電話連絡をした上、必要な提出書類を明確にしてから申請準備するのが大切です。
準備が必要な書面の場合、早めのご用意が必要になることから対応できる体制を整えておく必要があります。
古物商許可の審査は40日程度かかりますので、早めに申請書類を明確にするようにしましょう。
ケース別の注意点
一軒家であるご自宅を営業所とする場合、特に問題なく許可取得が可能です。特に登記簿謄本の提出も求められることはありません。
ご自宅が分譲マンションの場合
分譲マンションの場合、マンションの管理組合が定める管理規約や使用細則にご注意ください。
分譲マンションの管理規約は、多くの場合国土交通省が策定した「マンション標準管理規約」に基づいており、区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないと定められているケースがあります。
この場合、分譲マンションであるご自宅で古物商許可を取得できるとしても、マンションの管理規約や使用細則等で事務所利用が制限されている可能性はあります。トラブルを避けるためにも管理組合に事前に確認することが必要です。
借上げ社宅の場合
ご自宅が借上げ社宅の場合、基本的には居住用で契約されているものと思います。
東京都や神奈川県等については、使用承諾書や賃貸借契約書等の提出まで求められませんので、例え借上げ社宅であるご自宅であっても古物商許可の取得自体はできますが、社宅の契約や規約には違反しないように注意しましょう。会社や管理会社から事前に承諾を得るようにしましょう。
家族内にすでに古物商がいる場合
同居の家族内に古物商がいる場合でも許可の取得は可能です。
ただし、許可取得後は家族であっても完全に別の古物商として管理が必要なので注意ください。例えば、在庫の保管場所、古物台帳の区分を明確にするなど、古物商として完全に別々にして、責任を明確にして管理することが大切です。
一部の管轄地域では、同居人にすでに古物商がいる場合には、営業所の間取りまで厳しくチェックを受け、独立性等に問題がないか確認される場合もありますので、事前に管轄警察署に電話して相談をする必要があります。
なお、例えば夫婦別々に古物商許可申請を行う場合に、同時申請を行うことも可能です。この場合、委任状を用意して、夫婦のどちらかが両者の分をまとめて古物商許可申請することも可能です。
掲示義務について(標識)
ご自宅を営業所にする場合であっても、古物商の標識(プレート)を営業所に掲示義務があります。
掲示する場所は「公衆の見やすい場所」と定められていて、通常、営業所の入り口等、通常街路等を通行する一般公衆において、社会通念上見やすいと認められる場所をいうとされます。
ご自宅を営業所にしている場合には、標識を掲示することに難色を示される方が多いのですが、掲示場所はご自宅の机の上や玄関、廊下などに掲示しても問題ないようです。詳細は管轄警察署にご確認ください。
自宅を営業所にした場合の古物営業の範囲と注意点
古物商は、行商を行う場合を除けば、原則営業所でしか古物の取引を行うことができません。
自宅を古物商の営業所とし、とくに他に営業所がない場合は、古物営業に関する業務はご自宅で行う必要があります。
たとえば、フリマアプリやネットオークションを利用して古物を売買する場合も、商品の管理や出品作業などは営業所として登録した自宅で行うことが原則です。
自宅(営業所)では業務に集中できないからとレンタルオフィスなどを別途借りて、それらの場所で業務を行わないようにしましょう。
ご自宅で古物商許可を取得したい方は当事務所にお任せください
当事務所では「自宅で許可が取れるか不安」といったご相談にも、丁寧に対応いたします。
自宅を営業所として古物商許可を取得する場合、管轄によっては警察から追加の説明や書類を求められることもあります。
当事務所では、自宅で営業される方へのサポート実績が多数あり、事前の要件確認から申請書類の作成、警察署との対応まですべてお任せいただけます。
まずはお気軽にご相談ください。下記フォームよりお問い合わせいただけます。
古物商許可に関するご依頼・お問い合わせ
土日・祝日・夜間も対応。