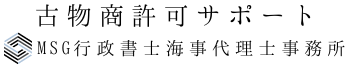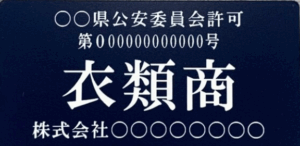古物商とは?
古物商とは、都道府県公安委員会による古物商許可を受けて、「古物」の売買又は交換、古物のレンタル等をする営業を営む者をいいます。古物商については古物営業法第二条3項、第二条2項1号、第三条等により具体的に定められています。
この古物商許可を受けずに、古物営業を営むと古物営業法三十一条により三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するとされます。
古物営業を営む場合には、事前に古物商許可を取得する必要があります。
「古物」の定義
古物商の取引の対象である「古物」は、古物営業法や古物営業法施行規則により定義されています。
古物営業法上の古物とは、「一度使用された物品」「使用されない物品で使用のために取引されたもの」「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」を指します。
したがって、例えば以下のようなものが古物に該当します。
- 一般的な中古品
- 小売店などから一度でも一般消費者の手に渡った物
- 物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理したものなど
また、「古物」は古物営業法施行規則により13区分に分類されています(例:機械工具類、衣類、自動車など)。取り扱う品がいずれの古物の区分に該当するかどうかは、許可取得の判断の上で重要です。
古物の13の区分については以下で紹介しています。
古物商許可が必要な取引
古物商許可を取得後は、古物の売買又は交換などの「古物営業」が可能になります。
古物商許可を受けていれば以下のような取引を営利目的で反復継続して行うことができます。
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取り修理して売る
- 古物を買い取り使える部品を売る
- 古物を買い取りレンタルする
- 古物を別の品物と交換する
単に「古物を売却すること」や「自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの」は古物営業に該当しないため、古物商許可を受けずとも行うことができます。
その他、以下のような取引にも古物商許可は不要です。
- 自分で使用していた物を売る
- 自分で使用するために購入したものを売る
- 無償でもらったものを売る
- 化粧品・お酒などの消費してなくなるもの
- 電子チケットなど実体がないもの
- 海外で購入したものを売る
古物営業法の趣旨は、盗品等の売買の防止やその速やかな発見などを目的としています。
法律により古物商許可が必要とされているのは、このように盗品の流通防止や盗品の発見が主な目的としています。
したがって、古物商許可が必要な取引は盗品を買取る可能性があるケースに限られます。
古物商になるには?申請手続きについて
古物商になるには、以下の必要書類を揃えて、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に直接提出し、都道府県公安委員会からの許可を受ける必要があります。
古物商許可取得に必要な書類一覧
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 本籍が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- URLの使用権原があることを疎明する資料
- 法人の定款コピー
- 法人の登記事項証明書
古物商許可の審査期間と費用
古物商許可を申請してから許可が下りるまで40日前後の期間がかかり、申請手数料として19,000円の納付が必要です。
なお、この古物商許可を得るには、古物営業法第四条で掲げる欠格事由に該当しないことが前提となります。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮刑・懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止中の営業、窃盗、背任、遺失物横領、盗品運搬等で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為等に関する法律の規定により公安委員会から命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条第1項(営業の停止)の規定によりその古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 心身の故障により古物営業を適正に実施することができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(一定の場合を除く)
古物商許可には更新制度はありませんので、一旦許可を受ければ更新手続きをせずに許可の維持が可能です。
個人の場合は、古物商許可の手続きの他にも、開業届・青色申告承認申請書を税務署に提出することで個人事業主として税務メリットを享受することができますので、開業届出の提出も忘れないようにしましょう。
古物商に課されている義務
都道府県公安委員会からの許可を受けて古物商となった後、古物商にはいくつかの法令上の義務が課されています。
具体的には古物商に次のような義務があります。
防犯三大義務① 取引相手の確認義務
古物商は、古物の買取などを行う場合には、次のいずれかの方法で取引相手の確認をしなければいけません。(例外品を除き、一万円未満の取引にはこの義務はありません)
- 取引相手から運転免許証などの身分証の提示を受けること
- 従業員等の面前で「住所、氏名、職業、年齢を自書した文書」を受け取ることなど
- 電子署名がされたメールなどを受け取ること
- その他、国家公安委員会規則で定めるいずれかの方法をとることなど
防犯三大義務② 取引記録の保存義務
古物商はその取引の都度、取引の内容などを帳簿に記録して3年間保存しなければいけません。(例外品を除き、一万円未満の取引にはこの義務はありません)
具体的には、以下の内容を帳簿に記録する必要があります。
- 取引の年月日
- 取引の古物の品目、数量
- 古物の特徴
- 取引相手の住所、氏名、職業、年齢
- 相手の真偽を確認するためにとった措置の区分
防犯三大義務③ 不正品発見時の警察への通報義務
古物商は、取引した古物に盗難品などの疑いがある場合には、警察官に申告する義務があります。
窃盗犯は窃盗した品物を換金するため古物商に買取を求めてくることがあります。
これを買い取ると、犯罪の証拠として提出を求められたり、損害を被ってしまうことになります。営業上の損害を回避するため、不正品を見極めて買い取りしないか、買い取ってしまったら直ちに警察に申告して対応することが必要です。
標識の提示義務
古物商許可を受けた場合、下記のような標識(プレート)を公衆の見やすい場所に提示しなければなりません。
なお、「公衆の見やすい場所」とは、営業所等の入り口や街路などを通行する一般公衆において、社会通念上見やすいと認められる場所をいいます。
自宅兼営業所の古物商の場合は、営業所の玄関や机の上等に掲示されている方が多い状況です。
出典:警視庁
許可証等の携帯義務
古物商は、「行商」又は競り売りをするときは、「許可証」を携帯する義務があります。
また、取引の相手から許可証の提示を求められたときは、これを提示する義務があります。
古物商許可申請は行政書士にお任せください
古物商許可が必要かどうかは、ご自身の取引内容によって異なります。「自分の場合はどうなのか」「今すぐ申請すべきなのか」など、判断に迷われることも多いかと存じます。
当事務所では古物商許可専門の行政書士がお客様の個別の事情を踏まえたアドバイス、必要書類の収集から提出代行までトータルサポートを行っています。ご依頼をご検討中の方は下記よりご相談ください。