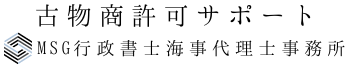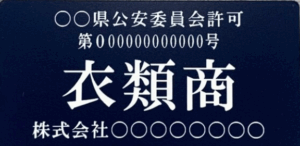個人申請と法人申請の違い
古物商許可は、個人でも法人でも取得可能です。基本的にはどちらで取得した場合でも同じです。
古物営業ができる内容も同じで、新規の許可申請時に公安委員会に納付する手数料も同額の19,000円です。
ただし、個人申請と法人申請では、許可を受ける名義が異なります。個人で取得する場合はご自身の名義で許可が下り、法人で取得する場合は法人名義で許可が下ります。
古物営業の内容そのものには違いはありませんが、許可主体が異なることにより、法人か個人かは明確に区別されるため、どちらで取得するかは状況に応じて慎重に選ぶ必要があります。
これは例えば、ある法人の役員が「個人」として古物商許可を取得した場合には、法人として古物営業を行うことはできません。一方で、「法人」として古物商許可を受けた場合には、その役員は個人としては古物営業を行うことはできません。
このように、古物営業法では許可を受けた本人以外がその名義を使って営業をすることを禁止しています。法人と個人間で古物商許可の名義貸し行為が行われると古物営業法違反に該当し3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
名義貸し行為は、古物営業法第三十一条の規定により、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するとされます。
さらに、この処分を受けた場合は、古物商の欠格事由に該当することになるため、古物商許可を取消しされるリスクもありますのでご注意下さい。
新規申請時の必要書類の違い
個人申請と法人申請では、新規の古物商許可申請時の必要書類にも違いがあります。
個人申請では下記の1~6までの書類が必要ですが、法人申請の場合には1~8までの書類の提出が必要です。
| 書類名 | 個人申請 | 法人申請 |
|---|---|---|
| 1.古物商許可申請書 | 要 | 要 |
| 2.略歴書 | 要(本人及び管理者のもの) | 要(役員全員及び管理者のもの) |
| 3.本籍入り住民票の写し | 要(本人及び管理者のもの) | 要(役員全員及び管理者のもの) |
| 4.誓約書 | 要(本人及び管理者のもの) | 要(役員全員及び管理者のもの) |
| 5.身分証明書 | 要(本人及び管理者のもの) | 要(役員全員及び管理者のもの) |
| 6.URLの使用権限資料 | 要(該当時のみ) | 要(該当時のみ) |
| 7.定款のコピー | 不要 | 要 |
| 8.登記事項証明書 | 不要 | 要 |
法人申請の場合には、定款のコピーや登記事項証明書に加えて、役員全員分の略歴書・誓約書・住民票等の書類が必要となります。
そのため、個人申請に比べて準備すべき書類が多く、手間もかかる傾向があります。
このような事情から、法人での申請は行政書士にご依頼いただくケースが一般的です。
法人と個人の両方で古物商許可を取得できる
古物商個人と法人の両方で古物商許可を取得することもできます。
個人と法人はそれぞれ独立した主体であるため、法人名義と個人名義でそれぞれ別々に古物商許可を持つことができます。
- 法人と個人の両方で管理者の掛け持ちはできません。すでにご本人が営業所の管理者となっている場合には、別の方に管理者をお任せする必要があります。
- 帳簿等の管理も個人と法人で明確に区別して管理・保管の必要があります。
切り替え手続きはない
古物商許可は、個人から法人、または法人から個人に切り替える手続きはありません。
したがって、名義を変える場合には、お手持ちの許可証を一度返納したうえで、新たに許可を取得する必要があります。
この場合、返納から新しい許可が下りるまでの間にタイムラグが生じるため、一時的に古物営業ができなくなります。
このような不都合を避けるために、事前に許可証の返納を約束し、新規の許可申請を警察署が先に受理する運用も行われています。切り替えを検討している場合は、事前に警察署に相談することをお勧めします。
よくある質問
- 副業で始めるなら個人と法人、どちらがおすすめですか
-
副業で古物商を始める場合は、まずは「個人」での申請がおすすめです。
理由は以下の通りです。
・個人申請は必要書類が少なく、登記も不要なため、スムーズに申請可能です。
・個人でも法人でも、古物営業法の観点から審査内容は基本的に同じです。許可の通りやすさに違いはありません。
・本業がある方や小規模に始めたい方にとって、まずは個人で始めて実績を積み、その後に法人化を考える方が現実的です。
- どちらの方が許可が通りやすいですか?
-
個人・法人ともに、許可取得の難易度に大きな差はありません。
どちらも、欠格事由に該当せず、必要書類が整っていれば基本的には許可されることが多いです。
ただし、法人申請は「役員全員」の書類の用意や略歴書なども必要なため、該当者の中に欠格事由があると全体が不許可になります。
その意味で、手続きの煩雑さや欠格事由への該当リスクという点では個人申請が若干有利です。 - 将来的に法人化するなら最初から法人申請が良いですか?
-
長期的に古物営業を本格的に展開する予定があるなら、最初から法人で古物商許可を取得するのも選択肢の一つです。
ただし、法人設立費用や法人の維持コスト(法人市県民税等の税務面)が発生するため、まずは個人で許可を取得後に軌道にのってから法人化をすること方がオススメです。
- 法人名義で古物商許可を取得していますが、今後は子どもに会社を引き継がせたいと考えています。古物商許可の扱いはどうなりますか?
-
法人の古物商許可は、代表者が交代しても原則としてそのまま継続できます。お子さんを新たに代表取締役に選任した上で、古物営業法上の代表者の変更届出を行えば、改めて許可を取り直す必要はありません。
ただし、新代表者が古物営業法上の「欠格事由」に該当する場合にはこの限りではありませんので事前の確認が重要です。
古物商許可の申請は行政書士にお任せください
当事務所では、個人・法人・外国籍の方などいずれの申請にも対応しており、申請者様の状況に応じて丁寧なサポートを心がけております。
副業で始めたい方、将来的な法人化を見据えている方、どなたでも安心してご依頼ください。
ご自身での申請に不安がある方は、ぜひ行政書士にご依頼ください。
面倒な書類の取得から申請書の作成、警察署への提出代行まで、トータルで対応可能です。